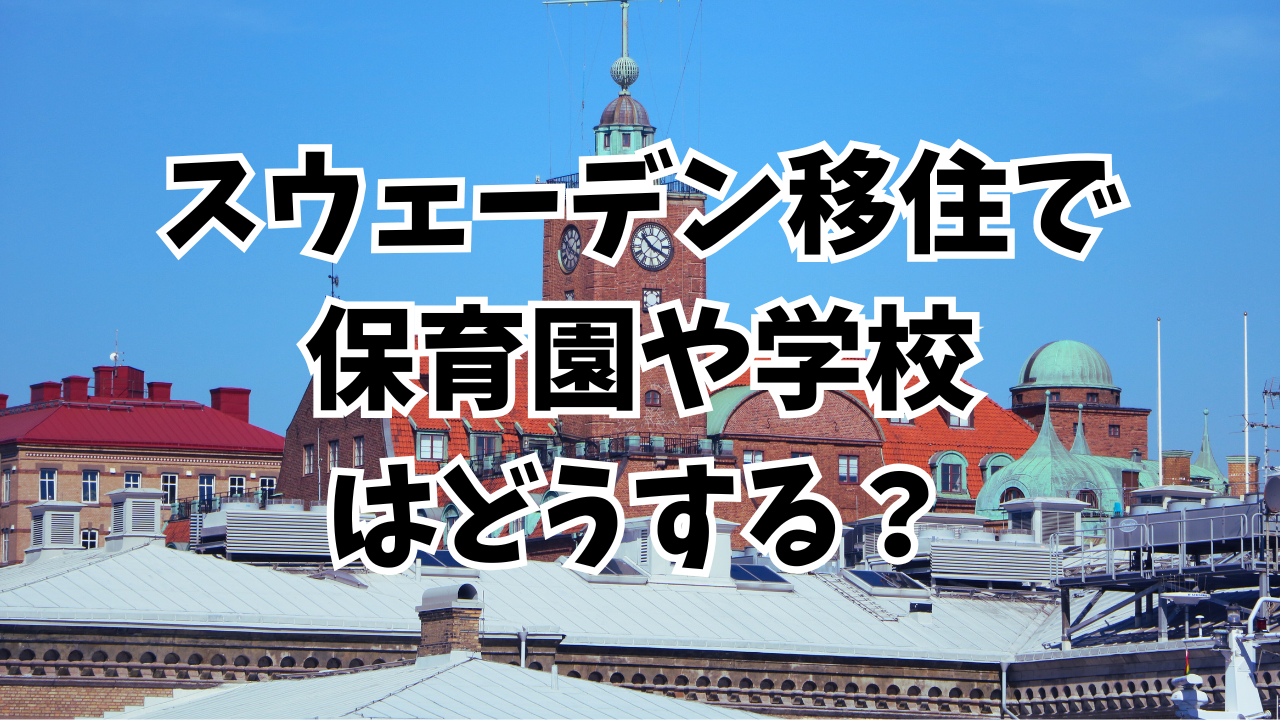「スウェーデンに子連れで移住したら、保育園や学校はどうなるの?」
そんな疑問を持つ方のために、今回はスウェーデンでの子育てに関する教育事情を、我が家の体験も交えながら丁寧にご紹介します。
保育園の入り方、小学校の仕組み、現地の言語環境、日本語教育とのバランス、そして費用のことまで。
観光では見えてこない「暮らす前提」での情報をまとめました。
特にお子さんが小さいうちに移住するご家庭にとって、教育の見通しが立つかどうかは大きな安心材料になりますよね。
この記事では、スウェーデンの教育制度の基本から、入園・入学に必要な手続き、現地でのサポート制度まで、リアルな視点で解説していきます。
スウェーデンの教育システムと学年制度の基本情報
まずはスウェーデンの教育制度と学年の仕組みについてご紹介します。
日本と比べると、スタート時期や進級制度などにいくつか大きな違いがあります。
全体像をつかんでおくと、今後の計画がぐっと立てやすくなりますよ。
スウェーデンの教育制度ってどんな感じ?
| 年齢 | 教育段階 | 備考 |
|---|---|---|
| 1〜5歳 | 保育園(Förskola) | 任意、所得に応じた負担 |
| 6歳 | 就学前クラス(Förskoleklass) | 義務教育の一環 |
| 7〜15歳 | Grundskola(義務教育) | 9年間、無料 |
| 16〜19歳 | Gymnasium(高等学校) | 進学率は90%超 |
スウェーデンでは、子どもが1歳から保育園(förskola)に通い、6歳で「就学前教育」を受け、7歳で義務教育がスタートします。
その後、9年間の義務教育(Grundskola)が続き、さらに多くの子どもたちが高等学校(Gymnasium)に進学します。
日本でいう小・中・高に相当するのが、以下のような流れになります。
 星野(妻)
星野(妻)わが家の長女も6歳で就学前教育に通い始めました。最初は「小学校じゃないの?」と思いましたが、遊びと学びが自然に混ざっていて、とても楽しそうでした。
義務教育の対象年齢と学年の仕組み
スウェーデンでは6歳から15歳までが義務教育であり、日本のような小・中学校という区切りはありません。
1年生から9年生まで一貫して同じ「Grundskola」として扱われます。
学年は基本的に子どもの生まれ年で決まるため、1月生まれと12月生まれが同じ学年になることも。
日本とスウェーデンの教育制度の違い
日本と比べて大きく違うのは、「早期教育」よりも子ども主体の学びを重視している点です。
小学校低学年でも、宿題は少なく、評価も絶対評価より成長の記録を重視するスタイルです。
「できた・できない」ではなく「どこまで理解しているか」を丁寧に見てくれる印象があります。
自動進級でサポートが充実
スウェーデンでは基本的に全員が自動的に次の学年へ進級します。
ただし、学習が遅れている子には個別のサポートが入り、補習や特別支援が制度的に用意されています。
「落第させる」のではなく「追いつけるように支える」考え方が徹底されています。
学校選びの選択肢が豊富
公立校が基本ですが、スウェーデンにはフリースクール(自由学校)という私立のような選択肢もあります。
教育方針が多様で、モンテッソーリやイマージョン教育など、家庭の方針に合わせて選べるのが魅力です。
私たちも移住後に見学して、「ここなら子どもが伸び伸び通えそう」と思える学校を選びました。
- 6歳から義務教育スタート(日本は小1が6歳)
- 一貫した9年制のGrundskola
- 学力評価よりも個人の成長重視
- 進級制度が柔軟でサポートが手厚い
- 公立以外にも教育方針の異なる学校が選べる
スウェーデン移住後の保育園・幼稚園の入園準備
小さなお子さんを連れてスウェーデンに移住されるご家庭にとって、保育園(förskola)選びと入園手続きは大きな関心事ですよね。
ここでは、私たち星野ファミリーの経験も踏まえながら、スウェーデンでの保育園の仕組みや手続き、言語サポートについて具体的にお伝えしていきます。
幼保一体型施設の特徴と利用方法
スウェーデンでは、いわゆる「幼稚園」と「保育園」の区別はありません。
Förskola(直訳すると「学校の前」)と呼ばれる幼保一体型の施設に1歳から就学前の6歳まで通います。
保育内容は、年齢に応じて「遊び」と「学び」をバランスよく取り入れたカリキュラムになっています。



うちの息子が通っていた園では、外遊び・音楽・簡単なクラフトが中心で、本人も毎日楽しみにしていました。
保育料の仕組みと世帯収入による影響
- 第一子:月額上限は約1,600 SEK(約22,000円)
- 第二子:半額
- 第三子以降:無料
保育園の利用は有料ですが、世帯収入に応じて金額が決まる仕組みになっています。
そして、スウェーデン全体で「上限額」が法律で定められており、それを超える負担にはなりません。
また、第二子・第三子はそれぞれ半額・無料といった配慮もあります。
何歳まで無料なのか、移住者の自己負担はどうなるのかについては、こちらの記事で詳しく解説しています!


入園手続きと必要書類
入園手続きは、住んでいる自治体(kommun)を通じてオンラインで申し込みます。
基本的にパーソナルナンバー(身分番号)が必要で、これが手元に届くまで手続きができないことが多いです。
申請の際には、以下のような情報や書類が求められます。
- パーソナルナンバー
- 住所・家族構成
- 希望する保育園(最大5園まで選択可能)
希望順で申請し、空き状況によって順次配分される形式です。
「どの園にも入れない」ということは基本的にないですが、希望順位に入れないケースもあります。
スウェーデン語が分からない場合のサポート
子どもがスウェーデン語を話せない場合でも、心配は不要です。
多くの園では外国人の子どもに慣れていて、言語サポートも充実しています。
最初はジェスチャーや簡単な英語で対応し、段階的にスウェーデン語を教えてくれるのが一般的です。
我が家も「最初は何も話せなかったのに、数ヶ月で日常会話ができるようになってびっくり!」という変化がありました。
日本とスウェーデンの保育環境の違い
| 項目 | 日本 | スウェーデン |
|---|---|---|
| 制度 | 保育園・幼稚園の区別あり | Förskolaに一本化 |
| 保育料 | 自治体により異なる | 全国共通で上限あり |
| 教育内容 | 年齢ごとのカリキュラム重視 | 遊びと探究の重視 |
| 外遊び | 天候によって中止も | 毎日実施が基本 |
| 言語対応 | 日本語が前提 | 外国人対応に慣れている |
日本の保育園に比べて印象的なのは、のびのびとした雰囲気と自然とのふれあいの多さです。
どんな天気でも外遊びが基本で、雨の日でもレインウェアを着て散歩に出かけます。
「遊び=学び」という考え方が徹底されているのが大きな違いでした。
日本とスウェーデンの子育ての違いについては、こちらの記事で詳しく比較しています。
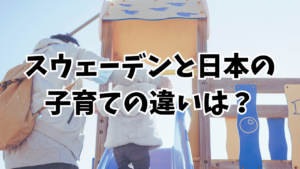
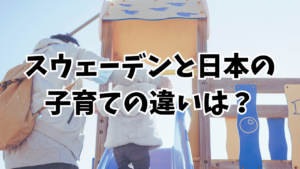
小中高入学の準備と入学可能な学校の種類
スウェーデンに子連れで移住する場合、小学生以上のお子さんがいるご家庭では、現地校・インターナショナルスクール・日本語教育など複数の選択肢を考えることになります。
ここでは、それぞれの特徴と入学準備に必要なポイント、そして教育費用についてまとめました。
無料で質の高い教育が受けられる現地校
スウェーデンの公立学校は学費無料であり、教材や給食まで基本的に無償で提供されます。
外国人の子どもでも、居住地の学区に自動的に割り当てられるため、特別な入学試験は不要です。
言語の壁はありますが、スウェーデン語教育のサポートが受けられるので、慣れるまで支援が続きます。



うちの長女も最初は「先生の話が分からない」と戸惑っていましたが、1年経った今ではスウェーデン語で友達と会話するほどに成長しました。
英語で学べるインターナショナルスクール
英語で授業を受けられる学校を希望する場合は、インターナショナルスクールという選択肢があります。
IB(国際バカロレア)を採用している学校も多く、進学や帰国を視野に入れている家庭には魅力的な選択肢です。
ただし、倍率が高く入学審査があり、学費もかかる点には注意が必要です。
日本語教育は家庭での工夫がカギ
スウェーデンでは、いわゆる「日本人学校」はストックホルムにしかなく、地方に住んでいる場合は選択肢が限られます。
そのため、多くの家庭では補習校に通わせるか、家庭での日本語学習に力を入れています。
わが家でも、読書・音読・日本語ワークブックなどを活用し、できるだけ楽しく続けられる工夫をしています。
スウェーデン特有の準備品って?
日本のような「ランドセル」や「制服」はなく、動きやすい服・外遊び用の防寒着・レインウェアが必須アイテムになります。
学校に持っていくのは、着替え袋・水筒・屋内シューズくらいで、とてもシンプルです。
最初は戸惑いましたが、「物を減らす=管理の手間が減る」という意味でとても助かっています。
教育費用と補助制度
| 種類 | 特徴 | 費用 |
|---|---|---|
| 公立現地校 | スウェーデン語、無償教育、地元密着 | 無料 |
| インターナショナルスクール | 英語中心、IB対応、外国人に人気 | 有料(数万SEK/年) |
| 日本語補習校 | 週末の日本語学習、日本人家庭向け | 一部費用あり |
| 家庭学習 | 家庭で教材や読書などを通じて学ぶ | 教材費のみ |
現地の公立校に通う場合、教育にかかる費用は基本的にゼロです。
インターナショナルスクールに通う場合は、年額で数万〜数十万SEKの学費がかかるため、家庭の方針と予算に合わせた選択が必要です。
また、通学に公共交通機関を利用する場合には通学定期券の補助が出ることもあります。
子供のスウェーデン語習得と学校生活のサポート
現地校に通うとなると、親として一番気になるのが「スウェーデン語は大丈夫かな?」ということだと思います。
言語の壁をどう乗り越えるか、学校や地域がどんなサポートをしてくれるのか、そして親としてできることも含めて、実体験を交えてご紹介します。
スウェーデン語を学ぶ環境
子どもにとっては、スウェーデン語はまさに「生活の中で学ぶ言語」です。
現地の学校に入ると、授業・遊び・給食の会話すべてがスウェーデン語になります。
ただ、子どもは適応が早く、半年〜1年ほどで日常会話レベルまで習得する子がほとんどです。



うちの息子も最初は「ママ、何て言ってるの?」と不安そうでしたが、今では発音だけは私よりもきれいです…!
現地の学校での言語サポート制度
スウェーデンでは、外国人児童向けに「スウェーデン語強化(SVA)授業」が用意されています。
通常授業とは別枠で、語彙・文法・聞き取りなどを基礎から学べるようになっています。
また、母語を維持するための「モデラスモール(母語教育)」という支援もあり、希望すれば日本語も対象になります。
外国人の子ども特有の悩みと対処法
言語だけでなく、文化や生活習慣の違いに戸惑う子も少なくありません。
「言いたいことが伝わらない」「友達ができない」といったストレスを感じることもあります。
そんなときは、学校のスクールカウンセラーや保護者支援担当(kurator)に相談するのが一般的です。
日本ほど堅苦しくなく、カジュアルに相談できるのも魅力です。
親ができる支援策と現地コミュニティへの参加
親としてできることは、子どもが安心できる居場所を家庭内につくること。
また、学校の保護者会や地域の子育てイベントに参加することで、子ども同士の関係もスムーズになりやすくなります。
我が家でも、近所の「ファミリーカフェ」に参加するようになってから、親子ともに友達の輪が広がりました。
異文化環境での子どもの適応プロセス
多くの子どもは、「最初は不安」→「理解できるように」→「自信がつく」という流れで徐々に適応していきます。
ただし個人差があるので、焦らず子どものペースに合わせて見守ることが一番大切です。
その過程で「うまくいかない日」もありますが、乗り越えた経験は子どもの大きな財産になります。
- 学校内にSVA(スウェーデン語強化)授業あり
- 母語教育(日本語)も申請で対応可能
- カウンセラーや支援担当が常駐
- 家庭や地域での安心できる環境づくりが大切
- 親の地域参加が子どもの適応を後押し