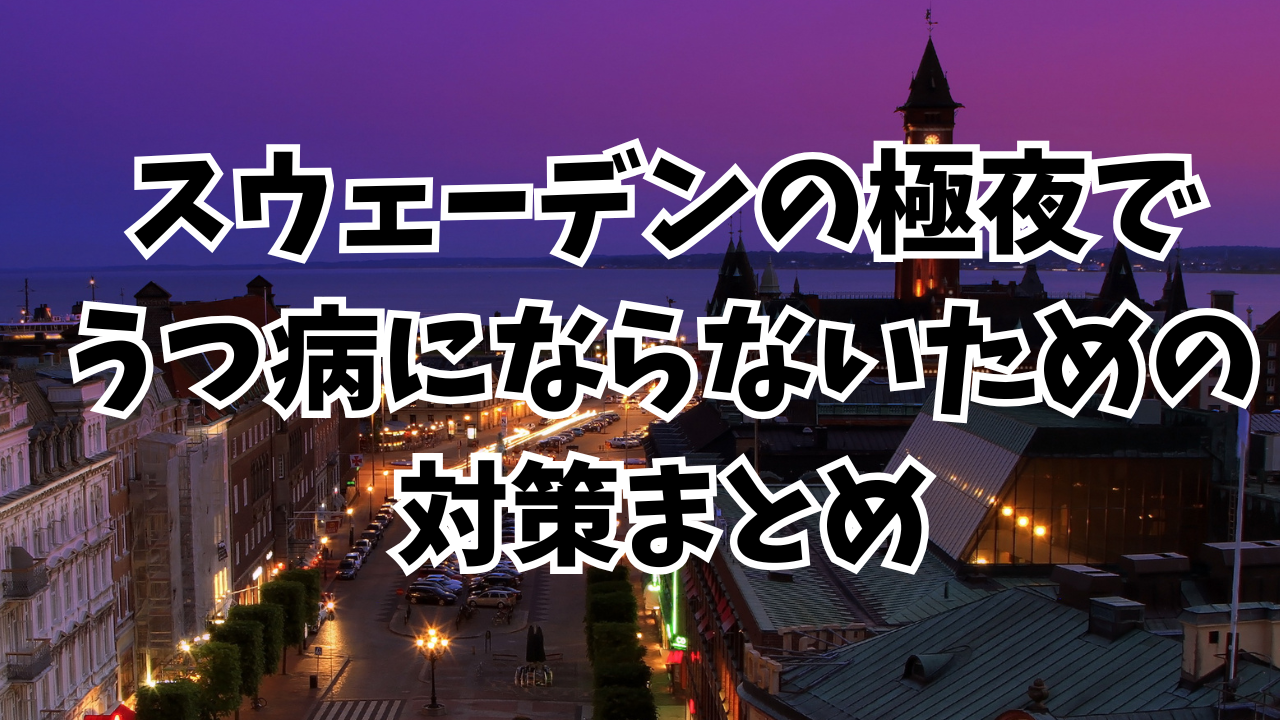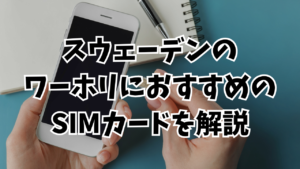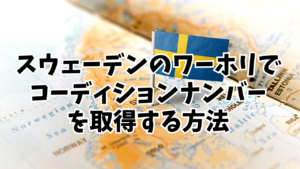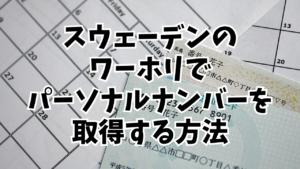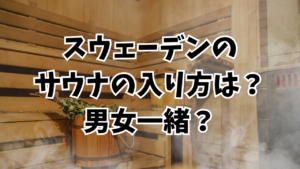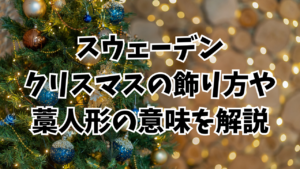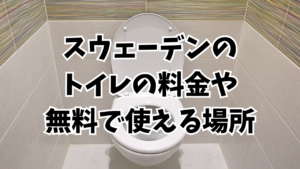スウェーデンの冬、とくに北部では「極夜(きょくや)」と呼ばれる長い暗闇の季節があります。
「ずっと日が昇らないって本当?」「そんな中でどうやって生活するの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。
実際、極夜の時期には「冬季うつ」や「気分の落ち込み」を訴える人も少なくなく、心と体への影響が気になるところです。
この記事では、
- スウェーデンの極夜とはどんな現象か
- 極夜が心と身体に与える影響
- うつ病を防ぐための基本対策と生活習慣
- 心を守りながら極夜を楽しむ過ごし方
などについて、実際にスウェーデンで4年暮らす私たち家族の体験も交えて詳しく解説していきます。
極夜とは?スウェーデンの暗い冬を理解しよう
「極夜(きょくや)」という言葉を初めて聞いた方もいるかもしれません。
これは北極圏に近い地域で起こる自然現象で、一定期間、太陽が地平線の下から昇ってこないという状態を指します。
スウェーデンでも北部のキルナやアビスコなどでは毎年冬になると極夜が訪れ、日中もずっと薄暗い日々が続きます。
南部に住んでいる私たちでも、冬は日照時間が極端に短くなり、朝9時ごろにやっと明るくなったと思ったら、午後2時にはもう夕方のような暗さになることも珍しくありません。
 星野(妻)
星野(妻)ヨーテボリに住んでいる私たち家族も、最初の冬はその暗さに本当にびっくりしました。時計を見て「まだ午後3時なのに夜みたい!」と娘が驚いていたのを覚えています。
極夜が起きる理由と期間
極夜は、地球の自転軸が傾いていることが原因で起こります。
北半球では、地球が太陽から遠ざかる冬の間、北極圏に近い地域では太陽の光が届かなくなる時間が長くなります。
スウェーデン最北部のキルナでは、12月中旬から1月上旬にかけて、本当に太陽が一切昇らない期間が続きます。
一方、ストックホルムやヨーテボリのような南部の都市では極夜まではいきませんが、日の出が9時ごろ、日没が15時前後という非常に短い日照時間になります。
身体と心に与える極夜の影響
光が少ない生活は、私たちの体にも心にも影響を与えます。
たとえば、体内時計のリズムが狂いやすくなり、朝スッキリ起きられない・夜眠れないといった不調が出やすくなります。
また、日光に当たる時間が少なくなると、幸せホルモン「セロトニン」や「ビタミンD」の生成が減るため、気分が落ち込みやすくなる傾向もあります。
これは「冬季うつ(季節性情動障害:SAD)」と呼ばれ、極夜のある地域では特に注意が必要です。
極夜がもたらすうつ病のリスクとは?
スウェーデンでは、極夜による気分の落ち込みを軽視していません。
実際、精神科やヘルスセンターでは、極夜に伴う抑うつ傾向の相談が増えるとされています。
具体的には、倦怠感・無気力・食欲の増加・日中の眠気などが主な症状です。
冬季うつのリスクは、特に日照時間の変化に敏感な人や、元々うつ傾向がある人にとって高まりやすいため、早めの対策が重要とされています。
極夜を乗り切るためのコツ
まずは、「極夜だからつらくなるのは自然なこと」と知っておくことが大切です。
そして、日光の代わりになるような光の取り入れ方や、生活リズムを整える工夫を日常に取り入れることが、極夜とうまく付き合う第一歩になります。
極夜でうつ病を防ぐための基本対策
スウェーデンの極夜を快適に乗り切るためには、「うつを予防する生活習慣」を意識的に取り入れることが大切です。
私たちも、暗さで気分が落ち込みそうなときには、光・生活リズム・栄養の3つを意識して整えるようにしています。
ここでは、日々の暮らしにすぐ取り入れられる5つの基本対策をご紹介します。



極夜のはじまりに合わせて、毎年我が家では「冬モード」の生活ルールを家族で確認しています。これだけでだいぶ気持ちが違いますよ。
極夜でうつ病を防ぐためのヒント
うつ症状の予防には、「意識して明るさを取り入れること」「体を動かすこと」「休息をとること」がポイントです。
スウェーデンの保健所(Vårdcentral)でも、冬季に心身の不調を感じたときは、まず生活習慣の調整を勧められます。
特別な機器や高額なアイテムがなくても、日常の中でできる工夫はたくさんあります。
光を生活に取り入れる工夫
まず第一に意識したいのが「光」です。
スウェーデンでは、極夜対策として朝から部屋を明るく保つことが推奨されています。
私たちも毎朝起きたらすぐにリビングの天井照明+間接照明+キャンドルライトをすべてつけて、意図的に「朝の光」を作っています。
- 起床後すぐリビングの照明をすべてON
- 朝食時はテーブルにキャンドルを灯す
- 窓際にライトを置いて部屋全体を明るく見せる
明るい環境にいる時間を増やすだけで、気分の落ち込みを感じにくくなるという研究もあります。日中はできるだけカーテンを開けて自然光を取り込むようにしましょう。
規則正しい生活が鍵
日照時間が短いと、体内時計がずれやすくなるため、「起きる時間・寝る時間・食事の時間」をなるべく一定に保つことが大切です。
とくに朝のスタートを整えることが、1日の気分に大きく影響します。
私たちも朝7時に照明とともに音楽を流し、子どもたちと一緒に朝ごはんを食べる習慣を守っています。
この「生活のリズム感」が、気分の安定につながっていると実感しています。
運動で幸せホルモンを増やそう
運動は、うつ病予防にとって非常に効果的です。
スウェーデンでは、冬でも日中に散歩することが習慣になっている家庭が多く、公園や森の小道には雪でも人が歩いているのをよく見かけます。
運動によってセロトニンやエンドルフィンといった「幸せホルモン」が分泌され、気分が前向きになりやすくなります。
子どもと雪道を歩いたり、ソリ遊びに付き合うだけでも十分な運動になりますよ。
ビタミンDで元気をチャージ
極夜の時期、ビタミンDの不足も問題になります。
スウェーデンでは秋以降、サプリメントでのビタミンD補給が一般的で、スーパーにも子ども用から大人用までさまざまな種類が並びます。
ビタミンDは、免疫力や気分の安定にも関わってくる栄養素なので、暗い冬こそ意識して摂取したい成分です。
小魚、卵、きのこなどの食品も取り入れつつ、必要に応じてサプリで補うのが無理のない方法です。
メンタルヘルスを守るための実践的なケア
極夜の時期は、物理的な暗さだけでなく、気分の落ち込みや不安感など心の問題も生まれやすくなります。
だからこそ、「心を整える時間」を日々の中に少しずつ取り入れることが大切です。
ここでは、私たち家族が実際に試してよかったと感じた、メンタルケアの実践法をご紹介します。



はじめは「こんなことで変わるの?」と思っていたのですが、小さな習慣を続けることで、気持ちが安定してきた実感があります。
光療法(ライトセラピー)の効果を体感
スウェーデンでは「光療法(ライトセラピー)」が非常に一般的です。
医療機関でも推奨されており、専用のライトを使って30分程度、朝に光を浴びるだけで、日中の気分が軽くなるといわれています。
我が家でもライトセラピー用のスタンドライトを購入し、朝の読書や朝食タイムに使うようにしています。
光療法は、セロトニン分泌を促し、体内時計のリズムを整えるとされていて、冬の朝の強い味方になっています。
ストレスを軽減するリラクゼーションの習慣
ストレスが蓄積すると、うつ症状につながる可能性も高まります。
そのため、毎日の中で「緊張を緩める時間」を意識的につくることが大切です。
スウェーデンの人々も、サウナやキャンドルタイム、足湯などでリラックスを大切にしています。
私たちも、夜にお気に入りのハーブティーを飲む時間を「一日の終わりの儀式」として楽しんでいます。
- お風呂上がりにストレッチをする
- 好きな音楽を聞きながら照明を落とす
- 香りのよい入浴剤やキャンドルを取り入れる
短い時間でも、「自分のための時間」を持つことで、心の疲れをじんわりほぐすことができます。
瞑想や日記で心の整理を
極夜の期間中、気分が沈みがちになる自覚がある人には、「書く」「静かに座る」といった内省的な習慣もおすすめです。
たとえば、5分間の瞑想や、「今日よかったことを3つ書く日記」は、ストレスケアとしてもよく知られています。
気持ちが整理されると、自分の感情に振り回されにくくなるだけでなく、「ちゃんと今日も過ごせた」という小さな自信にもつながります。
専門家に相談するタイミング
「どうしても気分が晴れない」「眠れない日が続く」と感じたら、無理せず専門家に相談することも大切です。
スウェーデンでは、Vårdcentral(保健センター)やオンライン診療を通じて、心理士や医師と話す機会を簡単に得ることができます。
特に「冬季うつ」については理解が進んでおり、受診に対するハードルも低めなので、抱え込まずに行動してみてください。
極夜を楽しみながら心の健康を保つアイデア
極夜の時期を「ただ耐える」だけでは、気分もふさぎこみがちです。
でも、スウェーデンの人々はこの暗い季節を「楽しみ」に変える工夫をたくさん取り入れています。
「暗いからこそできること」「暗いからこそ心地よいこと」を見つけることで、極夜の過ごし方がぐっと前向きになるのです。
ここでは、実際に私たちが試してよかった「心を温める冬の楽しみ方」をご紹介します。



最初の年は「暗いなあ」と思うことが多かったのですが、意識して楽しみを増やすようにしてから、冬の時間がぐっと愛おしくなりました。
キャンドルや間接照明で暖かな空間作り
スウェーデンでは、キャンドルやライトで「光を楽しむ文化」が根付いています。
家の窓辺には必ずと言っていいほど7本アーチのキャンドルスタンドや星型のライトが飾られ、夕方になると一斉に点灯される街の風景はとても幻想的です。
我が家でも、LEDキャンドルやフェアリーライトを使って、部屋ごとに「光の雰囲気」を変えて楽しんでいます。
- 天井照明を控えめにして間接照明を活用
- 窓辺にキャンドル型ライトを置いて外からの光景も楽しむ
- 夕食後のリラックスタイムにフェアリーライトでやさしい明かりを
明かりを工夫するだけで、部屋の雰囲気も気分もがらりと変わります。
ヒュッゲな時間を楽しむ工夫
「ヒュッゲ(Hygge)」は、スウェーデンの隣国デンマークから来た言葉ですが、「心地よく穏やかな時間」という意味で、スウェーデンでも共感される価値観です。
たとえば、好きな本を読みながら温かい飲み物を飲む時間や、家族でボードゲームを囲む夜など、ささやかな時間に喜びを見つけるスタイルです。
こうした暮らしの楽しみ方が、極夜の中での精神的な安定にもつながっているのだと思います。
新しい趣味を見つけることで心を豊かに
暗くて外出しづらい季節こそ、「室内で楽しめる趣味」を持つことが大きな支えになります。
我が家では、この季節に合わせて子どもと一緒に刺繍や料理に挑戦するようになりました。
他にも、パズル・読書・手芸・語学学習・お菓子作りなど、明るい時間を気にせず没頭できる趣味はたくさんあります。
気がつけばあっという間に1日が過ぎていて、「暗いから退屈」と感じにくくなりました。
家族や友人との交流で孤独感を防ぐ
極夜は、どうしても「内向き」になりやすい季節です。
そんな時こそ、人とのつながりを意識して持つことが、心の支えになります。
スウェーデンでも、冬の間にホームパーティや「フィーカ(お茶の時間)」を楽しむ文化があります。
私たちも、週末に友人家族と「ホットチョコレートとワッフルの会」を開いたり、家族で一緒に冬の映画を見る日を決めたりして、寒さの中に温かさを感じる工夫をしています。
極夜でも前向きに過ごすためのヒント
極夜の季節は、「どう乗り切るか」だけでなく、「どう前向きに過ごせるか」が心の健康を保つ鍵になります。
光や運動などの対策に加えて、日々の中での達成感や自然とのふれあいを取り入れることで、冬の暗さもまた豊かな時間に変わっていきます。
この章では、日常の中でできる前向きな工夫をご紹介します。
小さな達成感を積み重ねる
極夜の時期は、何をしてもやる気が出ないと感じることがあります。
そんなときは、「小さな達成感」を意識的に積み重ねていくのがおすすめです。
たとえば、ベッドを整える・朝食をつくる・10分だけ散歩するといった些細なことでも、「今日もできた」という感覚が自信になります。
我が家では、ホワイトボードに「今日やったことリスト」を書いて、子どもたちと一緒にチェックしています。



私自身、暗い時期を「苦手な季節」から「少し楽しみな季節」に変えられたのは、小さな喜びや達成感を意識するようになってからです。
自然に触れる時間をつくる
太陽が出なくても、外の空気や自然にふれることは、気分のリフレッシュにとても効果的です。
スウェーデンでは、雪景色や森の中を歩くことで心が落ち着くと信じられており、真冬でも公園や湖の周辺を散歩する人が多くいます。
わが家でも、午後の少しだけ明るい時間を見つけては、近所の森を歩くようにしています。
自然の中では、気温の低さや暗さも不思議と気にならなくなるんですよね。
スウェーデンの冬ならではの文化を楽しむ
最後に、極夜の時期こそ体験できる「スウェーデンの冬の文化」を楽しむことも、前向きに過ごすコツのひとつです。
たとえば、ルシア祭(12月)やユール(クリスマス)など、冬には家族や地域で祝う伝統行事が多くあります。
特にルシア祭では、子どもたちがキャンドルを持って歌う行列を見ると、寒さや暗さを忘れて心が温まります。
また、グロッグ(温かいスパイスワイン)やペッパーカーカ(ジンジャークッキー)など、冬限定の味わいもこの時期ならではの楽しみです。
- 「できたこと」を記録して達成感を可視化
- 毎日15分でも自然にふれる時間を確保
- ルシア祭やクリスマスなど行事を楽しむ
暗さを「欠点」ではなく「冬の味わい」ととらえる視点が、極夜とうまく付き合う最大のヒントということですね。