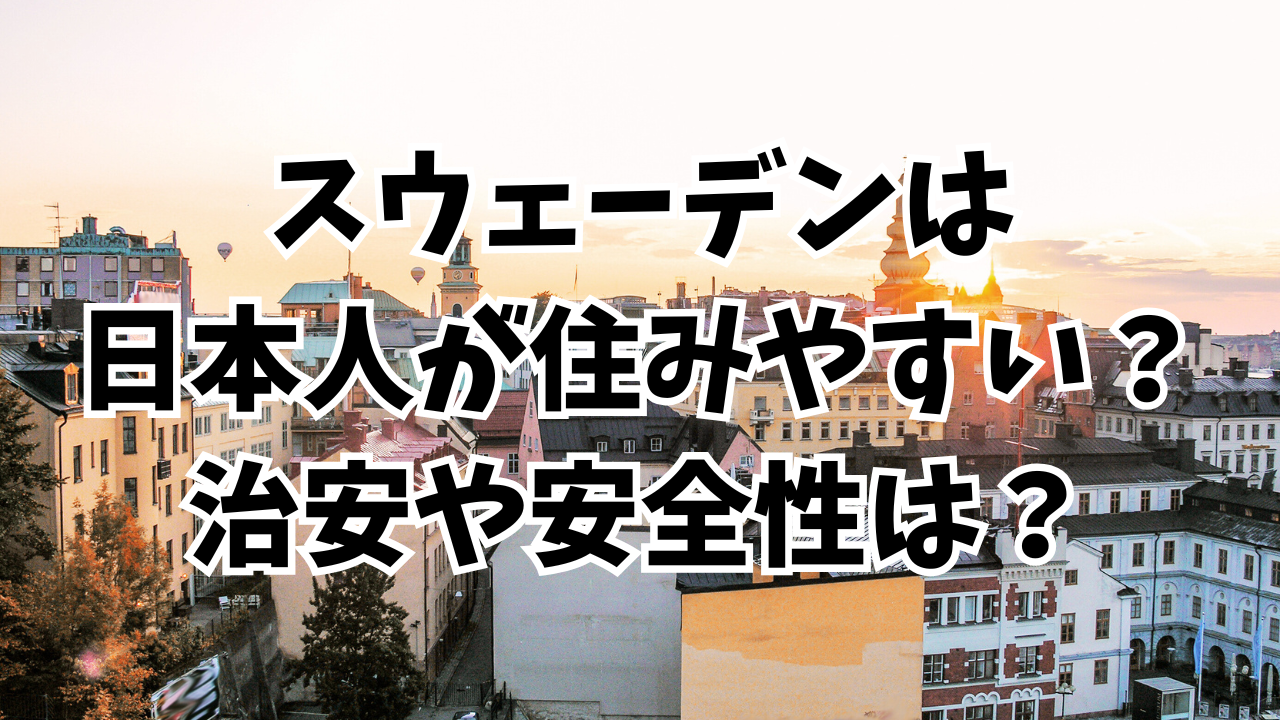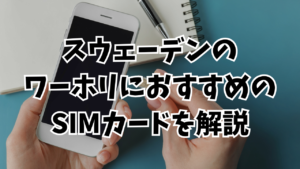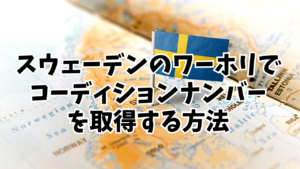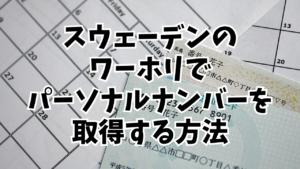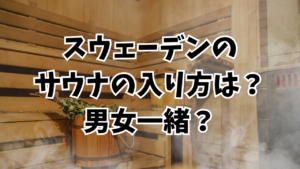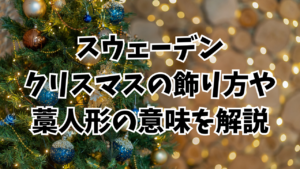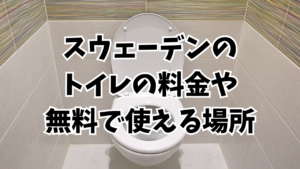海外に住むとなると、気になるのが「本当に日本人にとって住みやすいのか?」ということ。
特に、治安や医療、教育、文化の違いなど、暮らしてみなければ分からない部分がたくさんありますよね。
私たち星野ファミリーも、家族4人でスウェーデンに住んで4年目になります。
最初は不安もありましたが、いまは「この国に来てよかった」と日々感じています。
この記事では、そんな私たちの実体験をもとに、日本人にとってスウェーデンが住みやすいと感じる理由や、安全性、生活の違い、移住者への支援制度について詳しくご紹介します。
旅行では見えない「暮らすからこそ分かる視点」で、スウェーデン生活のリアルをお届けします。
日本人でもスウェーデンが住みやすい理由
スウェーデンに住んでみて実感するのは、「外国人だから」と構えすぎずに暮らせる安心感です。
ここでは、私たちが実際に暮らしてみて「これは日本人にとって住みやすい」と感じたポイントを4つご紹介します。
社会福祉の充実
スウェーデンといえば、福祉国家として有名ですよね。
実際、医療・教育・育児支援が手厚く、暮らしを支える安心感があるのは確かです。
特に私たちがありがたかったのは、子どもの医療費がほぼ無料なこと。
予防接種や診察、処方薬なども基本的に公的負担でまかなわれ、家計に優しい制度が整っています。
 星野(妻)
星野(妻)息子が冬に咳が止まらなくなったときも、家庭医にすぐ診てもらえ、薬も無料でした。「お金の心配なしに医療を受けられる」ことの安心感は大きいです。
働きやすい環境
夫が最初に感じたのが、「働き方の違い」です。
スウェーデンでは、定時退勤・有給取得・在宅勤務が当たり前の文化で、家族や自分の時間を大切にする働き方が根づいています。
長時間労働やサービス残業の概念はほとんどなく、仕事と生活のバランスをとることが高く評価される風土です。
自然との調和した生活
スウェーデンは国土の多くが森や湖に囲まれており、都市に住んでいても自然と触れ合える機会が豊富です。
週末には家族で近くの森へハイキングやピクニックに出かけるのが定番。
「自然と共に暮らす」感覚が、子育て中の私たちにはとても心地よく感じられます。
教育制度と文化的な安心感
スウェーデンの教育は、日本と比べると競争が少なく、自分のペースを尊重する傾向があります。
私たちの娘が現地校に通い始めたとき、「成績」よりも「考え方や人との関わり方」を重視する教育方針に驚きました。
また、先生との距離が近く、子どもの気持ちをしっかり聞いてくれる点も安心材料のひとつです。
- 医療や教育などの基本的なサポートがしっかりしている
- 無理のない働き方と個人の尊重が浸透している
- 自然や地域とのつながりが強く、孤独を感じにくい
- 教育現場でのストレスが少なく、子どもも適応しやすい
こうした点が積み重なって、「日本人でも安心して暮らせる」と感じられるのだと思います。
日本人が暮らせるほどの治安の良さと安全性は?犯罪率は?
海外移住を考えるうえで、治安の良し悪しはとても気になるポイントですよね。
スウェーデンといえば「安全そう」というイメージを持つ方も多いと思いますが、実際に暮らしてみて分かることもたくさんあります。
このパートでは、日本人目線で感じるスウェーデンの治安や安全性について、具体的な体験も交えてご紹介します。
スウェーデンの治安って、安心できるの?
基本的にスウェーデンの治安は良好で、日常生活に不安を感じる場面はほとんどありません。
もちろん、都市部ではスリや自転車の盗難などの軽犯罪はゼロではありませんが、身の危険を感じるようなことは稀です。
私たち家族も、夜の公園を歩いたり、子どもと一緒に買い物に出かけたりと、安心して行動できています。



娘が学校帰りにひとりで近所のスーパーに寄ったときも、心配なく見守ることができました。日本と同じとは言いませんが、「子どもが自分で動ける安心感」は確かにあります。
スウェーデンの治安や、日本人が暮らしやすい理由についてもっと詳しく知りたい方はこちら!
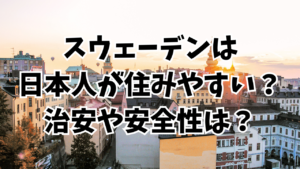
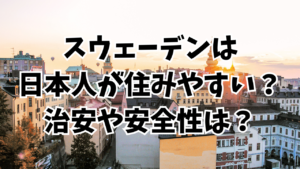
女性や子供にも優しい環境
スウェーデンはジェンダー平等が進んでおり、女性や子どもが一人で行動しても自然な社会です。
例えば、ベビーカーを押していると、バスや電車でさっと席を譲ってくれることが日常茶飯事。
子ども連れの外出に対する配慮が行き届いているので、ママでも気兼ねなく動ける環境が整っています。
住民間の信頼感と対話文化
スウェーデンでは、「他人を信じる」ことが社会の前提として根づいています。
近所の人とも「おはよう」「今日は寒いね」と自然に声をかけ合う習慣があり、地域のつながりが治安の安定にも一役買っています。
困ったときに「すみません」と声をかければ、たいていの人は快く助けてくれる雰囲気があります。
- 夜道でも人通りがあり、街灯が明るい
- 子どもだけで通学・外遊びが可能な地域が多い
- 公共交通機関の中でもトラブルが少ない
- 事件よりも「忘れ物が戻る」ほうが話題になる
もちろん油断は禁物ですが、「子育て世代が落ち着いて暮らせる国」として、スウェーデンの安全性はとても高いと感じています。
日本とスウェーデンとの生活の違い
日本での暮らしに慣れていると、スウェーデンでの日常は驚きの連続です。
けれども、それは決して「大変」という意味ではなく、「考え方の違いに触れる楽しさ」として感じられることが多いです。
ここでは、私たちが実際に生活して感じた、日本とスウェーデンの大きな違いを3つの視点からお伝えします。
ライフバランスの重視
スウェーデンで暮らしていると、「暮らしのために働く」という価値観が根づいているのを強く感じます。
仕事よりもプライベートを大切にする文化があり、休暇の取得や家族との時間が本当に尊重されています。
例えば、夏のバカンス期間は丸1ヶ月休む人も少なくなく、メールもオフになるのが当たり前。
日本で感じていた「常につながっていないといけない」プレッシャーから解放され、私たち夫婦も少しずつリズムを整えていきました。



移住当初、夫が「Slackの通知が来ないんだけど…」と戸惑っていたのを思い出します。実際、みんな本当に休んでいるんです。
ビジネススタイルの違い
職場でのやり取りも、日本とは大きく違います。
スウェーデンでは上下関係がフラットで、立場に関係なく意見を言い合うのが普通。
「黙って従う」よりも「納得して協力する」姿勢が大切にされるので、コミュニケーションの質にも違いが出てきます。
会議も短くて効率的で、「その場で決まる」スピード感には驚かされました。
食文化や生活習慣の比較
食事の面でも、日本とスウェーデンはかなり違います。
代表的な違いは、朝食とランチの位置づけ。
スウェーデンでは朝からパンやチーズ、コーヒーでしっかり食べ、ランチは温かい料理を食べる文化があります。
一方で、夕食は17時台と早めで、家族全員でテーブルを囲む時間を大切にしています。
- 仕事中心 → 生活中心(バランス重視)
- 上下関係重視 → フラットな関係性
- 夕食は20時前後 → 夕食は17〜18時が一般的
- 挨拶にお辞儀 → 握手や「ヘイ!」のカジュアルな声かけ
どちらが良い悪いではなく、違いを知ることで選択の幅が広がるのが海外生活の醍醐味だと感じています。
日本人がスウェーデンで生活できる工夫は?
言語も文化も異なるスウェーデンで、日本人が長く安心して暮らしていくにはちょっとした「コツ」があります。
ここでは、実際に私たち家族が工夫してきたことや、現地で出会った日本人移住者の知恵を交えて、暮らしのヒントをお伝えします。
日本食や日本文化の楽しみ方
海外で暮らしていても、日本食が恋しくなる瞬間ってありますよね。
スウェーデンにも、アジア食材店や大型スーパーで日本の調味料や乾物が手に入ります。
特にストックホルムやヨーテボリには、品揃えが豊富な店舗も多く、日本の食品を買うのに困ることは少ないです。
また、家庭での和食づくりや、おにぎり・お味噌汁などを子どもと一緒に作る時間は、心を落ち着かせてくれる大切なひとときになります。



週末に娘と「納豆を作ってみよう!」とチャレンジしたこともあります。多少におっても(笑)、やっぱり和食はホッとします。
地域の外国人コミュニティ活用
スウェーデンには、外国人をサポートするネットワークがたくさんあります。
市役所や図書館で開かれる無料の「移住者向け講座」や「子育てカフェ」などは、地域に馴染むための入口としてとてもありがたい存在です。
また、Facebookなどでは日本人同士が情報交換できるグループもあり、困ったときやちょっとした質問にも気軽に応じてもらえます。
スウェーデン語学習の重要性
生活に慣れてくると痛感するのが「言葉の壁」です。
日常会話程度の英語で生活はできますが、公的手続きや子どもの学校とのやり取りではスウェーデン語が求められる場面が多くなります。
スウェーデンではSFI(Swedish for Immigrants)という無料の語学教育プログラムがあり、私たちも最初はここからスタートしました。
- 和食・季節行事を家庭で取り入れる
- 地域の外国人支援プログラムに参加する
- SFIや語学アプリで日々少しずつスウェーデン語に慣れる
完璧を目指す必要はありませんが、「分かろうとする姿勢」があるだけで、現地の人との距離がぐっと近くなります。
こうした日々の小さな積み重ねが、日本人がスウェーデンで心地よく暮らすための支えになっていると感じています。