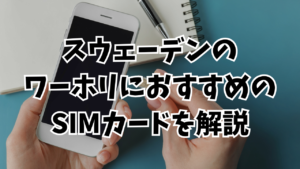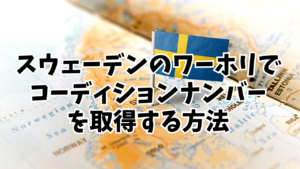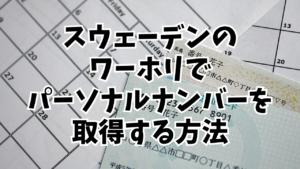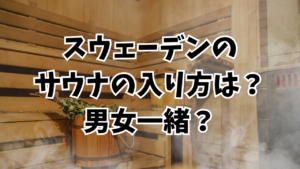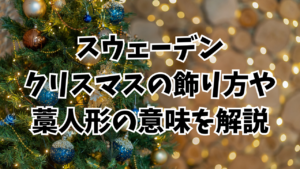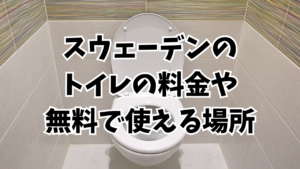「スウェーデンに移住したいけれど、本当に満足できるのかな?」
そんな不安を感じている方に向けて、この記事では星野ファミリーの実体験をもとに、スウェーデン移住のリアルなメリットとデメリットをまとめてご紹介します。
私たち家族は日本からスウェーデンへ移住して4年目。
現地の保育園・学校・医療制度・住宅事情まで、暮らしてみなければ分からなかった「よかったこと」「ちょっと困ったこと」がたくさんあります。
憧れだけでは決められない移住だからこそ、事前に知っておきたい「ギャップ」や「後悔しやすいポイント」も含めて、正直にお伝えします。
旅行とは違う、日々の生活に根ざした視点での発見が、きっとあなたの判断のヒントになるはずです。
スウェーデン移住を決めた理由
私たち星野ファミリーがスウェーデン移住を決めた背景には、「北欧の暮らし」に対する長年の憧れと、子どもたちにとってよりよい環境を求めたいという気持ちがありました。
ここでは、どんなきっかけでスウェーデンを選んだのか、そして移住を後押しした制度や価値観について詳しくお伝えします。
留学や転職で移住を考える人が多い背景
私たち夫婦はそれぞれ20代の頃にスウェーデンへワーキングホリデーで滞在しており、その時の経験が大きな原点でした。
英語が通じること、治安が良いこと、多様性が尊重される社会など、初めての海外生活でも安心して暮らせた記憶が残っています。
近年では、ITや教育の分野でスウェーデンに関心を持つ日本人が増えており、リモートワークや国際案件をきっかけに転職→移住というパターンも珍しくありません。
期待した理想の生活とのギャップ
移住前は「のびのびとした暮らしが待っている」と期待していましたが、実際に住んでみると、気候・言葉の壁・コミュニケーションの取り方など、慣れるまでに苦労した点もありました。
理想と現実のギャップを感じる瞬間はありましたが、その違いをどう受け止めるかが移住生活の鍵だと感じています。
 星野(妻)
星野(妻)「理想と違ってた…」とがっかりするより、「へぇ、こういう考え方なんだ」と面白がれると、気持ちがぐんとラクになりますよ。
スウェーデン特有の文化や価値観の魅力
スウェーデンの魅力は、制度や景観だけでなく、人々の考え方や空気感にもあります。
たとえば「LAGOM(ラゴム)」という言葉には「ちょうどいい暮らし」の哲学が込められていて、過度な競争や消費を避けて、無理なく心地よく生きていく姿勢が感じられます。
その価値観に私たちも共感し、もっと家族の時間を大切にしたいと考えるようになりました。
社会福祉や教育制度が移住を後押しする理由
スウェーデンの移住を現実のものにした決め手は、社会福祉制度と教育の手厚さでした。
子どもたちにプレッシャーの少ない教育環境を提供できること、医療費や保育料の負担が少ないことは、家族にとって大きな安心材料になりました。
保育園や学校では、「できる・できない」よりも「自分の気持ちを言えること」が大切にされています。
自然との共存とサステナビリティ政策
スウェーデンでは、自然との共存が生活の中心にあります。
都市部でもすぐ近くに森や湖があり、週末には家族でハイキングやピクニックに出かけるのが日常。
また、リサイクルやエコライフへの意識が高く、子どもたちも学校で「持続可能な暮らし」を自然に学ぶ環境が整っています。
- ワーホリ時代の経験からくる安心感
- 家族の時間を大切にしたいという想い
- 社会福祉・教育制度の手厚さ
- 自然と共存する生活とサステナビリティ
- 理想のライフスタイルに近い価値観
こうした背景が重なり、私たちは「やっぱりスウェーデンで暮らそう」と、家族での移住を決意しました。
スウェーデン移住のメリット
スウェーデンでの生活には、日本ではなかなか得られない魅力がたくさんあります。
特に子育て中の私たち家族にとって、環境の違いは生活の質を大きく変えるものでした。
ここでは、実際にスウェーデンに住んでみて「これは移住してよかった」と感じた点を5つに分けてご紹介します。
充実した社会福祉制度と子育てサポート
スウェーデンの福祉制度は、生活の土台としてとても心強い存在です。
子どもに関しては、保育園の月額上限が決まっていて、兄弟がいれば割引もあります。
医療費も18歳までは基本無料で、予防接種や検診も丁寧に行ってくれます。
親が安心して働けるように、育児休業も男女どちらにも手厚く保証されていて、夫も現地でパパ育休を経験しました。



夫が育休を取ったとき、「ママだけが育てる時代じゃない」というスウェーデンの考え方に心から納得できました。
スウェーデンの育児制度の特徴や、日本との違いを詳しく知りたい方はこちら↓
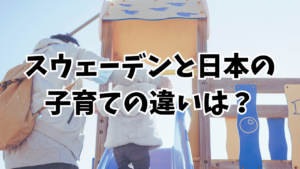
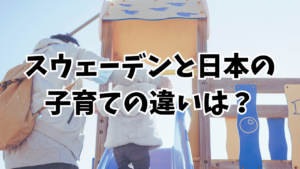
働き方改革が進んだ職場環境
スウェーデンの企業では、長時間働くこと=評価されるという考え方がありません。
むしろ、効率的に仕事をこなし、プライベートの時間をしっかり確保する人が評価される傾向にあります。
リモートワークの導入も早く、柔軟な働き方が当たり前になっています。
夫も以前より早く帰宅できるようになり、家族との時間が格段に増えました。
英語が通じやすい環境
スウェーデン人のほとんどが英語を流暢に話せるため、日常生活で困る場面はあまりありません。
役所・病院・スーパーなどでも、英語での対応がスムーズなので、移住初期の不安を大きく和らげてくれました。
ただし、子どもが学校に通うようになると、スウェーデン語の習得はやはり重要になってきます。
スウェーデンでの言語事情や、日本人がスウェーデン語を習得する難易度について知りたい方はこちら↓
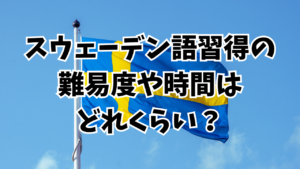
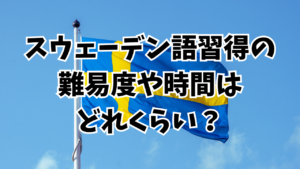
近代的な都市と豊かな自然のバランス
ストックホルムやヨーテボリのような都市部でも、自然がすぐそばにあるのがスウェーデンの魅力です。
街中の公園や緑地、週末に車で30分ほど走れば湖や森。
子どもたちも自然の中で遊ぶことが当たり前になり、スクリーンから離れる時間が増えました。
日常生活で感じる自由と平等の精神
スウェーデンには、「人それぞれでいい」「誰もが尊重されるべき」という価値観が根づいています。
服装・働き方・家族の形など、「こうでなきゃダメ」という圧力が少なく、心の自由度が高いです。
特に子育てをしていると、周囲からの干渉が少ない=のびのびと育てられることを実感します。
- 子育て支援と福祉制度の手厚さ
- 効率と柔軟性を重視した働き方
- 英語で通じる社会インフラ
- 都市生活と自然との絶妙なバランス
- 個性が尊重される自由な空気
このようなメリットが重なって、「移住してよかった」と思える場面は日々の暮らしの中にたくさんあります。
スウェーデン移住のデメリット
スウェーデンでの暮らしには確かに多くのメリットがありますが、「理想通り」とは限らないのも現実です。
ここでは、実際に生活してみて感じた不便さや戸惑い、そして事前に知っておけば心構えができたなと思った点を正直にお伝えします。
厳しい冬の寒さと日照時間の短さ
冬の寒さと暗さは、日本とは比べものになりません。
特に11月〜2月は日照時間が短く、朝8時を過ぎても真っ暗、午後3時にはすでに日が沈むという日々が続きます。
気温も氷点下が当たり前で、防寒対策や心のリズム調整が必要です。



最初の冬は、気分が落ち込んでしまった日もありました。対策としては、意識的に散歩に出たり、室内を明るくしたりするのがおすすめです。
生活費の高さと物価の上昇
スウェーデンはヨーロッパの中でも物価が高い国です。
特に外食、日用品、住居費などは日本より高く、日々の出費がかさみがち。
インフレの影響もあり、ここ数年で光熱費や食費がさらに上がったと感じています。
まとめ買いやセール活用など、家計管理に工夫が求められます。
住民同士のなじめなさや排他的な環境
スウェーデン人は控えめで穏やかな人が多い一方で、プライベートな距離を大切にする文化があります。
そのため、初対面で打ち解けるのに時間がかかることも。
「よそ者」として疎外感を覚えることがあるのは正直なところです。
移民政策が引き起こす治安への懸念
一部の大都市では、移民受け入れの急増により地域格差や治安への影響が指摘されるようになっています。
とはいえ、日常生活の範囲で身の危険を感じるようなことはほとんどありません。
住むエリア選びや時間帯の意識など、基本的な注意を心がければ、安心して生活できます。
給与やキャリアの停滞の可能性
スウェーデンでは年功序列や昇給文化があまりなく、昇進よりも「安定して働けること」に価値を置く傾向があります。
特に移住者はスウェーデン語力や現地経験が評価されづらく、キャリアの成長スピードが遅くなることも。
転職や副業がしやすいとは言えない環境でもあるため、「のんびり構える余裕」も必要かもしれません。
- 長く暗い冬による気分の落ち込み
- 外食・生活必需品の物価の高さ
- 人間関係が築きづらい文化的距離
- 一部地域での治安への不安
- キャリア形成の難しさ・昇給の停滞感
こうした点も含めて理解しておくことで、「想定外だった…」という後悔を防ぎやすくなると思います。