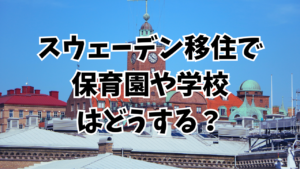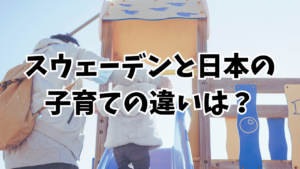「スウェーデンでは子どもの医療費が無料らしいけど、それって何歳まで?」「日本人が移住したら、すぐその恩恵を受けられるの?」
そんな疑問を持っている方に向けて、この記事ではスウェーデンの医療費制度の仕組みをわかりやすく解説していきます。
特に、子連れでスウェーデンに移住を検討されている方にとって、「医療費の負担がどれくらい軽くなるのか」は大切なポイントですよね。
我が家も実際に移住を経験し、日本との違いに驚いたり安心したりと、たくさんの発見がありました。
この記事では、子どもの医療費が無料になる条件、自己負担が発生するタイミング、移住者が注意すべき手続き、そして高福祉を支える社会構造まで、実体験を交えてご紹介します。
スウェーデンで子供の医療費無料は何歳まで?
まずは最も気になる「スウェーデンで子どもの医療費が無料なのは何歳までか?」という点から見ていきましょう。
この制度は、スウェーデンらしい「子ども中心の福祉」を象徴する仕組みのひとつです。
子供の医療費が無料なのは18歳まで
スウェーデンでは、子どもの医療費は原則として18歳の誕生日の前日まで無料です。
これは、病院での診察・処方箋・入院など、一般的な医療行為の大部分が対象となります。
18歳未満であれば国籍に関係なく「住民登録」されていれば無償なので、移住後に登録さえ完了していれば安心です。
 星野(妻)
星野(妻)うちの長女が風邪を引いたときも、窓口で支払いがなくて「本当にこれでいいの?」と戸惑うほどでした。
無料の対象になる医療サービスは?
具体的には以下のような医療サービスが無料対象となります。
- 家庭医(Vårdcentral)での診察
- 専門医の紹介受診
- 公立病院での入院・手術
- 小児科・歯科(20歳まで無料)
- 処方薬(一定額までは無償)
ただし、成人と同じく完全な「全額無料」ではなく、一部の薬や特定の検査には上限付きの自己負担が発生するケースもあります。
住民登録がカギになる
この医療費無償の恩恵を受けるには、「スウェーデンの住民登録(Folkbokföring)」が必須です。
移住直後は、登録手続きとパーソナルナンバー(個人番号)の発行を待っている間、制度を受けられないこともあります。
特に急病に備えて、移住初期は一時的な医療保険を検討するご家庭も多いです。
スウェーデンの高福祉を支える仕組み
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0〜17歳(18歳誕生日前日まで) |
| 対象者 | 住民登録済みの子ども(国籍問わず) |
| 無料範囲 | 診察、入院、歯科、処方薬など |
| 注意点 | 住民登録前は対象外、一部自己負担あり |
なぜこんなに手厚い制度が実現しているのか。
それは、高い税負担と公的医療への信頼がベースになっているからです。
スウェーデンでは、所得税や消費税(25%)を通じて、医療・教育・保育といった社会保障全般を支えています。
その分、受けられるサービスが手厚く、子育て世代にとって非常に暮らしやすい国になっています。
スウェーデン移住者の日本人が知っておくべき医療制度
スウェーデンの医療制度は非常に充実していますが、移住したばかりの日本人にとっては戸惑う点も多いのが実情です。
ここでは、実際に私たち家族が経験した手続きや注意点をもとに、「住民登録前後でどう変わるのか」「短期滞在との違い」など、移住者が押さえておくべき情報を整理しました。
まずは住民登録が最優先
スウェーデンの医療制度を利用するには、住民登録(Folkbokföring)が大前提です。
これは、日本でいう「住民票登録」のようなもので、登録されて初めてパーソナルナンバー(個人識別番号)が発行されます。
この番号がないと、医療機関の予約や支払いがすべて「外国人価格(全額自己負担)」扱いになってしまうため、早めの申請が大切です。



私たちも移住当初、子どもの発熱で慌てて予約を取ろうとした際に「パーソナルナンバーがないと受診できない」と言われて冷や汗をかきました。
移住直後に注意したいこと
住民登録から番号の発行までには、1〜2週間〜1ヶ月程度かかることがあります。
この期間中は、スウェーデンの公的医療サービスが原則利用できないため、以下のような対策が必要です。
- 日本の海外旅行保険に加入しておく
- クレジットカード付帯保険を活用する
- 現地で民間医療保険に入る
観光や短期滞在の人は要注意
スウェーデンでは90日以内の滞在者は住民登録できません(※ビザがない場合)。
つまり、観光・短期留学・短期出張の人は、医療費を全額自己負担することになります。
病院によっては、外国人向けに「特別料金」が設定されていることもあります。
念のため、クレジットカードの付帯保険や海外旅行保険に入っておくのが安心です。
長期居住者なら医療費の負担を軽減できる
住民登録が完了すれば、子どもだけでなく大人も医療費の上限制度の恩恵を受けられます。
大人は完全無料ではないものの、年間負担額に上限があり、それを超えると自己負担がなくなります。
この点については後ほど詳しく解説します。
子どもや家族全員分の登録を忘れずに
- 住民登録(Folkbokföring)がすべての基盤
- 登録完了前は医療費全額自己負担
- 90日以下の短期滞在では無料制度の対象外
- 家族全員分の手続きを個別に行う必要あり
- 保険や渡航前の準備が重要
住民登録は「世帯単位」ではなく「個人単位」です。
そのため、両親+子ども1人1人すべてに対して申請が必要になります。
特に生まれたばかりの赤ちゃんは、渡航後に出生証明やビザ関連の書類提出が必要となる場合があるので、早めの準備をおすすめします。
スウェーデンで18歳以上の場合の医療費事情
子どもは18歳まで医療費が原則無料ですが、18歳を超えるとどうなるのかも気になるところですよね。
ここでは、18歳以降の医療費負担の仕組みや、自己負担額の上限制度、慢性疾患を抱える人に安心な制度まで、スウェーデン特有の考え方と制度を解説します。
18歳を超えるとどう変わる?
18歳の誕生日以降は、医療費に自己負担が発生します。
一般診療(Vårdcentral)では、1回の診察につき約200〜300SEK(約3,000〜4,500円)が目安です。
ただし、この負担は一定額を超えると軽減される「上限制度」があるため、高額になりすぎることはありません。
年間自己負担額の上限がポイント
スウェーデンには「高額医療費保護制度(Högkostnadsskydd)」という仕組みがあり、年間の自己負担額が上限に達すると、それ以降の診療は無料になります。
2025年現在、上限は以下の通りです。
- 医療費(診療):1,300SEK(約20,000円)
- 医薬品(処方薬):2,850SEK(約44,000円)
この制度のおかげで、慢性疾患のある方や頻繁に通院が必要な方でも安心して医療を受けられます。
公的医療保険がしっかりカバー
スウェーデンには日本のような健康保険証の提示はありませんが、住民登録とパーソナルナンバーにより、自動的に公的医療制度に加入している状態になります。
そのため、診察時には特別な手続きなく、公的料金で診療を受けることができます。
もちろん、私立病院やプライベートのクリニックもありますが、費用は高めになる傾向があります。
長期治療も安心な「ハイコストプロテクション」
医薬品に関しても、一定額を超えた後は段階的に割引率が増加し、年間上限に達すると無料になります。
このような仕組みを「ハイコストプロテクション」と呼び、患者が経済的理由で治療を中断しないように配慮されています。
特に糖尿病や喘息など、継続的な服薬が必要な場合には大きな安心感があります。
医療費と生活設計のバランス
| 内容 | 詳細 |
|---|---|
| 診療費 | 1回200〜300SEK程度 |
| 医療費の上限 | 年間1,300SEK(診療)、2,850SEK(薬) |
| 支払い方法 | 現地のIDで自動適用、公的保険に自動加入 |
| 補助制度 | ハイコストプロテクション(高額負担軽減)あり |
スウェーデンの医療制度は、「基本は自己負担、でも困ったときは守る」という考え方に基づいています。
高額になることはほぼなく、生活設計にも取り入れやすい制度です。
移住を検討されている方は、最初の1年の保険設計と、パーソナルナンバー取得後の上限制度の使い方を意識しておくと安心です。
家賃や食費、公共料金などを含めたスウェーデンの1ヶ月間の生活費の目安については、こちらの記事をチェックしてみてください。


スウェーデンの福祉制度の背景とその仕組み
ここまで読んで、「どうしてスウェーデンはここまで手厚い医療制度が実現しているの?」と思われた方も多いのではないでしょうか。
この章では、スウェーデンの医療制度を支える社会的・歴史的な背景と、制度を維持するための仕組みについてご紹介します。
スウェーデンの医療費負担の歴史的な背景
スウェーデンの医療制度の原型は、第二次世界大戦後の福祉国家政策によって形成されました。
戦後の復興期に、「誰もが等しく医療を受けられる社会」を目指し、全国民に平等な医療アクセスを保障する方向へと舵を切ったのです。
その流れを受けて、1980年代には子どもの医療費無償化が進められ、今の制度の基盤ができあがりました。
地方自治体が医療を運営しているって知ってました?
日本では国の制度が強く関与しますが、スウェーデンでは医療の実務を運営しているのは地方自治体(Region)です。
それぞれの地域が、医療施設の運営や医師の配置、医療費の管理を担当しています。
そのため、地域によって細かいルールや窓口が違うこともあります。



引っ越した先の自治体で診療の予約方法が異なっていて、最初は「同じ国でもこんなに違うの?」と驚きました。
「公平性」を重視した医療システム
スウェーデンの医療制度の大きな柱は「公平性」です。
年収や社会的地位にかかわらず、誰もが同じ医療を、同じ価格で受けられることを徹底しています。
また、B「困っている人を優先する」という考え方が根底にあり、医療のリソースは本当に必要な人へ優先的に配分されます。
これにより、医療の効率と質のバランスが保たれているのです。
子供の医療費無料は何のため?
子どもの医療費が無料なのは、単に親の負担を減らすためだけではありません。
国家としての投資であり、「子どもが健康に育つことが、社会全体の利益になる」という長期的視点によるものです。
たとえば、病気を早期に発見・治療することで将来の医療費を抑える効果も期待されています。
収入を問わない制度維持の課題と工夫
こうした手厚い制度を収入や保険料に関係なく維持するには、当然コストがかかります。
スウェーデンでは高い消費税(25%)や所得税がその財源を支えています。
しかし、国民の多くがこの仕組みに納得しているのは、「税金がちゃんと自分たちに返ってくる」と感じているからだと思います。
- 戦後の福祉国家政策を背景に誕生
- 地方自治体が実務を担う分権型システム
- 公平性を重視し、誰でも同じ医療を受けられる
- 子どもへの投資として医療費を無償化
- 高税率でも納得感のある再分配制度
医療制度を含めたスウェーデン移住のメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています!