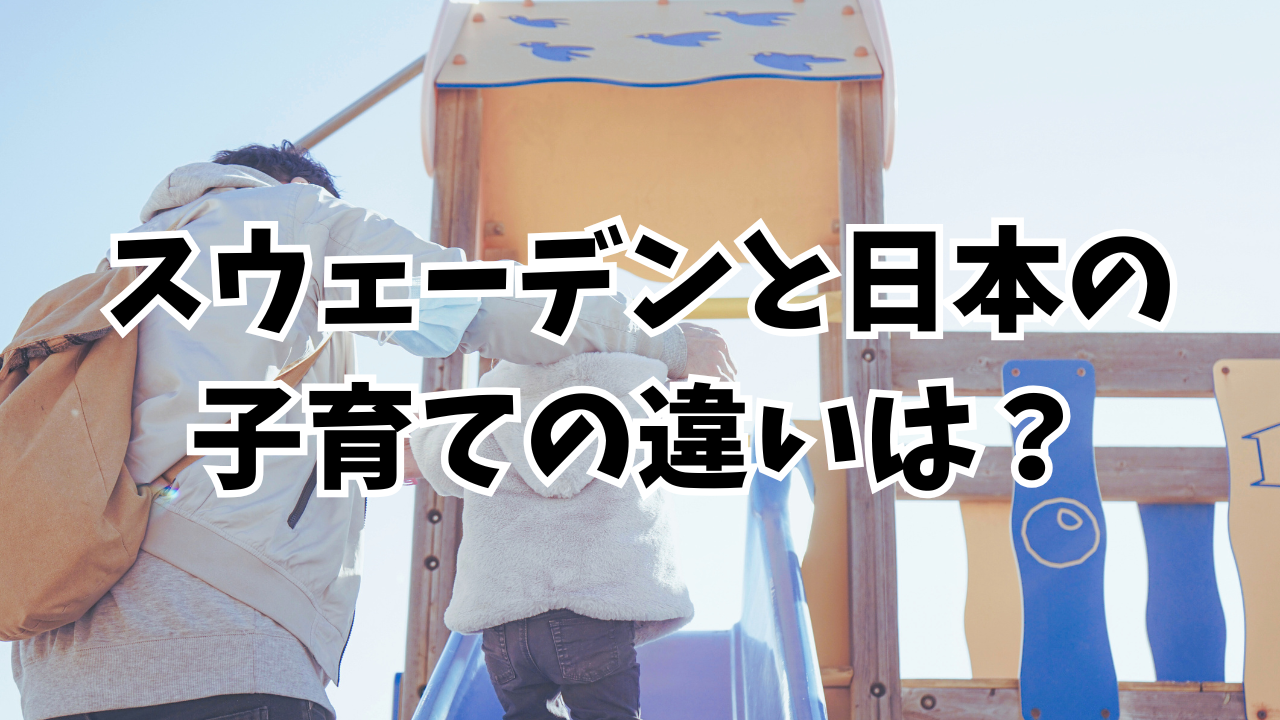「スウェーデンでは男性も当たり前に育休を取るって本当?」
そんな疑問を持つ方に向けて、今回は日本とスウェーデンの育児環境の違い、特に男性の育休取得率に焦点を当ててお話しします。
日本でも制度は整いつつありますが、現実には「取りたくても取れない」という声が多く聞かれます。
一方、スウェーデンでは男性が積極的に育休を取得し、家族と過ごす時間を大切にする文化が根付いています。
その背景には、制度の違いだけでなく、社会全体の考え方や職場文化、生活の中の価値観が大きく影響しています。
私たち星野ファミリーも、日本で子育てをした経験があるからこそ、スウェーデンに来てから感じた「ギャップ」に驚きの連続でした。
この記事では、リアルな体験を交えながら、両国の子育て環境の違いや、スウェーデンで男性が自然と育休を取れる理由について丁寧にご紹介します。
日本とスウェーデンの育児環境の違い
まずは、私たちがもっとも驚いた日本とスウェーデンの「育児を取り巻く環境」の違いから見ていきましょう。
制度や文化、社会の価値観など、さまざまな要素が親の行動や選択に影響を与えています。
育児休暇制度の違いにびっくり
日本にも育児休暇制度はありますが、正直に言って「使われていない制度」という印象が強いです。
特に男性の場合は、制度上は取得可能でも、実際に育休を取る人はごく一部。
一方、スウェーデンでは男女ともに育休を取得するのが「当たり前」という感覚です。
しかも、その取得期間も平均で数ヶ月から1年と、日本よりはるかに長く、柔軟です。
育児休暇が「特別なもの」ではなく、ライフサイクルの中に自然に組み込まれている印象でした。
 星野(妻)
星野(妻)実際に夫が育休を取得したとき、周りのスウェーデン人からは「普通すぎて話題にならない」という反応でした。
職場環境と文化の影響
日本では「育休=職場に迷惑をかけるもの」という空気感が根強いですよね。
実際、私たち夫婦も日本で働いていたとき、育休について話題にすること自体に躊躇がありました。
しかし、スウェーデンでは育児に関わるのが社会人として当然という空気があり、職場もそれを支える体制ができています。
たとえば、同僚が突然休むことになっても「お互いさま精神」でカバーし合う文化が根付いているのです。
社会の風潮と育児支援
育児は「家族の問題」ではなく「社会全体で支えるもの」という考え方が、スウェーデンではしっかり浸透しています。
自治体や保健センターも含め、あらゆる場所で育児に関する情報が得られ、相談しやすい雰囲気があります。
日本でも自治体による支援はありますが、「積極的に情報を探さないと支援にたどり着けない」という印象が強かったです。
子育てにかかるコストの違い
子育てには何かとお金がかかりますが、この点でも大きな違いがあります。
スウェーデンでは、保育料は収入に応じて決まる上限付きで、二人目以降はさらに割引。
医療費も子どもは18歳まで無料なので、安心して健診や通院ができます。
日本では医療費助成はあるものの、自治体によって差があり、保育料も高額になることが多いです。
- スウェーデン:育休は自然、制度も柔軟
- 日本:制度はあるが活用しづらい空気
- スウェーデン:職場・社会の支援体制が整っている
- 日本:支援はあっても届きにくい印象
スウェーデンの育児制度の特徴
次に、スウェーデンで育児がしやすいと言われる理由の根幹にある制度面の特徴を詳しく見ていきましょう。
実際に暮らしてみて、「こんな制度まであるの!?」と驚いたことがたくさんあります。
世界初の男女共通育児休業制度
スウェーデンは1974年に世界で初めて「男女共通」の育児休暇制度を導入した国です。
それ以前は「母親専用」の制度だったのを、父親も同じように育児に関われるよう改革しました。
この変化は単なる制度改正ではなく、「父親も子育てするのが当たり前」という文化を作る大きな一歩だったのです。



1970年代にここまで進んでいたと知ったとき、日本とのタイムラグに衝撃を受けました。
「パパ・クォータ」の仕組みと効果
スウェーデンには「パパ・クォータ(父親割当制)」というユニークな仕組みがあります。
これは、育児休暇のうち一定期間を父親が取らないと、その期間の給付が失効するという制度です。
つまり、取らないと「損」になるので、自然と男性も育休を取るようになります。
この制度は導入以降、男性の育休取得率を飛躍的に高める効果を発揮しました。
公的保育制度がめちゃくちゃ便利
スウェーデンの保育制度も、子育てを支える大きな要素です。
1歳から保育園に入れるうえ、先ほども触れたように保育料は所得に応じて決まるため、家計への負担が少ないのが特徴です。
また、保育園側も家庭と協力して育てる姿勢が強く、子どもに無理をさせない柔軟な対応をしてくれます。
我が家でも、息子が登園しぶりを見せたとき、先生が「今日は少し短めで大丈夫ですよ」と言ってくれたことがあり、心が軽くなりました。
子育てしやすい国ランキング常連の理由
- 男女共通の育児休業が制度として根付いている
- 父親が育休を取らないと損をする「パパ・クォータ」
- 保育料は収入に応じて上限付き
- 保育現場が柔軟で親に寄り添ってくれる
- 社会全体で子育てを支える文化がある
スウェーデンは「子育てしやすい国ランキング」で常に上位にランクインしています。
理由は制度の手厚さだけでなく、育児に対する社会全体の姿勢が前向きだからです。
「子どもが泣いていても責められない」「ベビーカーでバスに乗るのが歓迎される」など、親が肩身の狭い思いをせずに済む社会の雰囲気があります。
日本人学校や現地の教育事情について詳しく知りたい方は、こちらの記事をチェックしてみてください!
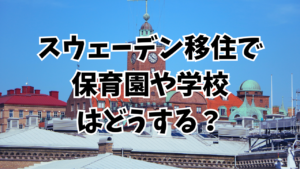
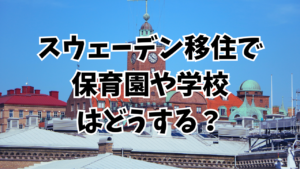
日本における男性育児休業の現状と課題
ここからは、日本における男性の育児休業の現状と、その課題について触れていきます。
制度自体は整っているものの、実際に育休を取得する男性はまだまだ少ないのが現実です。
制度はあるけど、なかなか活用されない現状
日本でも男性の育児休業取得は法的に認められており、育児休業給付金も支給されます。
しかし、2023年時点のデータでは、男性の取得率はようやく17%程度。
これは「制度があるのに活用されない」典型的なパターンだと感じます。
多くの家庭で「取りたくても言い出せない」「復帰後の立場が不安」という声が根強くあるのです。



私の周囲でも「育休は取らない前提で計画を立ててる」という家庭が多く、ちょっともったいないなと思っていました。
職場文化がハードルに
制度だけでなく、職場文化も大きな障壁になっています。
日本では「仕事優先」がいまだに根強く、男性が長期休暇を取ると「戦力ダウン」と捉えられがち。
また、管理職や同僚が育休に理解を示さないケースも少なくありません。
これは制度よりもむしろ「空気」の問題といえるでしょう。
男性が育児に参加するメリット
実際に夫がスウェーデンで育休を取得して感じたのは、家族関係がぐっと深まったという点です。
乳児期の赤ちゃんのお世話はもちろん、上の子の送迎や遊び相手など、父親ならではの関わり方が家庭にプラスの影響を与えました。
また、子どもの成長をリアルタイムで一緒に見守れるというのは、育児の大きな喜びの一つだと思います。
海外事例に学ぶ日本の課題
- 取得率は徐々に上昇も、まだ約17%と低水準
- 「空気」によって申請をためらうケースが多い
- 家庭・育児への参加が父親自身にもメリットあり
- 制度だけでなく、使いやすい職場環境がカギ
スウェーデンのような海外の成功事例を見ると、日本にも活かせるヒントは多いです。
たとえば「パパ・クォータ」のような取得を促す制度設計や、復帰しやすい職場文化の形成が重要です。
ただ制度を増やすだけでなく、それを活かすための現場レベルの意識改革が求められていると感じます。
移住者が後悔しないためのポイントや、日本とスウェーデンの生活の違いについては、こちらで詳しく紹介しています!


スウェーデンで男性の育休取得率が高い理由
では、なぜスウェーデンではここまで男性の育休取得が一般的になっているのでしょうか?
そこには、制度的な仕組みだけでなく、社会的・文化的な背景が複雑に絡み合っています。
私たちが実際に暮らして感じた、「これは大きい!」と思った要素を4つに分けてご紹介します。
経済的な給付の安心感
スウェーデンでは育児休業中の給付が手厚く、最大で給与の約80%が支給されます。
しかも有給日数に応じた取得の分割が可能で、必要に応じて週に数日だけ取得することもできます。
この柔軟性と金銭面のサポートが、男性にとっても「現実的に取りやすい」と感じられるポイントです。



我が家でも、夫が育休を取る際に給付の仕組みを確認して「これなら生活に支障がないね」と納得できたのが大きかったです。
男女平等の意識が根付いている
スウェーデン社会では「性別に関係なく育児は平等に行うべき」という意識が当たり前に存在しています。
男性がベビーカーを押していたり、スーパーで子どもと買い物していたりする光景は、まったく珍しくありません。
「父親が育児する=かっこいい・当然」という価値観が根付いているので、誰も気負わずに休暇を取ることができるのです。
男性育児への啓発がしっかりしている
スウェーデンでは、政府が積極的に「父親の育児参加」を啓発するキャンペーンを実施しています。
市町村レベルでもパンフレットやセミナーが用意されていて、育児に対する知識や心構えを自然と身につけられます。
さらに、学校教育やテレビ番組などでも育児参加が当たり前という描き方がされており、次世代の価値観形成にもつながっています。
国と企業が一緒になって取り組む
スウェーデンで男性育休が当たり前の理由
| 要素 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 経済的支援 | 給与の約80%が保障され、分割取得も可能 |
| 文化的背景 | 男女平等意識が強く、育児は父母どちらも担当するという価値観 |
| 国の啓発活動 | 政府・自治体による育児参加キャンペーンや教育の影響 |
| 職場の柔軟性 | チームで支え合う職場文化と企業の理解 |
スウェーデンでは、国の制度と企業の姿勢が連動して機能している点も見逃せません。
企業側も育児休業を前提とした働き方を制度化しており、チームでフォローし合う文化がしっかり根付いています。
「一人抜けたら困る」ではなく、「みんなで回す」ことが組織の前提になっているのです。
日本とスウェーデンの男性育休を比較して見えてくるもの
ここまでの内容を通して、日本とスウェーデンの男性育休に対する姿勢と現実の違いがかなり明確になってきたと思います。
単に「育休取得率が違う」という表面的な話ではなく、そこにはそれぞれの国の文化・制度・価値観が深く関係しています。
「制度はある」の先にある壁の存在
日本でも育児休業の制度は整備されており、給付金などの仕組みもあります。
けれども現実には、「制度を使う側が職場で不利になる」という“見えない圧力”が壁になっています。
スウェーデンのように「育休を取らないと逆に不自然」となるには、社会全体の意識変化が必要です。



夫がスウェーデンで当たり前のように育休を取っている姿を見て、「これが本来の自然な姿なのかもしれない」と感じました。
子どもにとっての「当たり前」が変わる
スウェーデンで子育てしていて感じるのは、子どもたちの価値観も自然と影響を受けているという点です。
パパが家事や育児をするのが普通な環境にいると、性別役割の固定観念が育ちにくくなります。
これは長期的に見て、ジェンダー平等を実現する大きな一歩でもあります。
「個人」の努力だけでは越えられない壁
日本では「頑張って制度を使おう」と思っても、個人レベルではどうにもならない問題に直面することがあります。
たとえば、復職後のキャリアへの影響や、上司の理解不足などです。
育休の取得を「権利として遠慮なく使える空気」ができてはじめて、制度が真に活かされると実感しています。
育児は「家族の問題」ではなく「社会の仕組み」
日本では育児が「各家庭の責任」とされがちですが、スウェーデンでは「社会全体で支えるもの」という考えが浸透しています。
だからこそ、制度を整えるだけでなく、誰もが安心して利用できる土壌づくりが重要になるのです。
日本とスウェーデンの男性育休における違い
| 項目 | 日本 | スウェーデン |
|---|---|---|
| 制度の有無 | ある(給付制度あり) | ある(1974年から運用) |
| 取得率 | 約17% | 約90%以上 |
| 職場文化 | 取得しづらい空気 | チームで支える文化 |
| 育休のイメージ | 遠慮・迷惑をかける | 当然・自然なこと |
| ジェンダー意識 | 男女で役割意識が残る | 平等が前提 |
男性の育休が家庭にもたらす変化
スウェーデンに住んで実感したのは、男性が育休を取ることが家庭全体にとってプラスに働くということです。
これは制度や数字だけでは見えてこない、暮らしてみて初めて分かるリアルな変化です。
夫婦間のパートナーシップが深まる
日本で子育てをしていたころは、私(妻)が中心になって育児を進めることが多く、知らず知らずのうちに「お願いする関係」になっていました。
でも、スウェーデンで夫が育休を取ったことで、ふたりで一緒に育てているという感覚が自然に生まれました。
お互いの大変さを理解し、感謝する機会も増えた気がします。



夫婦でおむつ替えや寝かしつけの工夫を話し合っている時間に、「チームになってるな」と実感しました。
子どもとの関係が深まる
父親が育児に関わる時間が増えることで、子どもとの関係も明らかに変わります。
特に乳児期の関わりは、その後の愛着形成にも影響があると言われています。
上の子も「パパが迎えに来てくれるのが一番うれしい」と言ってくれるようになり、安心感のある存在としての信頼が深まりました。
家族としての一体感が強まる
毎日の生活を一緒に過ごす時間が増えると、家族の一体感が自然と生まれます。
週末だけ一緒にいるよりも、平日のルーティンの中に父親がいることが、子どもにとっても親にとっても大きな意味を持ちます。
「家事も育児も一緒にやる」が習慣になれば、家庭の空気もやわらかくなるのを実感しています。
将来の価値観にも影響を与える
子どもたちは親の姿を見て育ちます。
だからこそ、「お父さんが家事も育児も自然にやっていた」記憶は、将来のジェンダー意識やライフスタイル選択に大きな影響を与えるはずです。
スウェーデンでは次の世代が「育児は一緒にやるもの」と自然に受け取る環境が整っています。
- 夫婦のパートナーシップが深まる
- 子どもとの信頼関係が強まる
- 家族としての一体感が育まれる
- 次世代の価値観形成に良い影響を与える